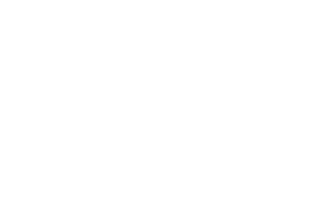No.001 神様を自称する男と女子高生
名前は何て言っただろう。
それは動物だったり乗り物だったりして、大きなバネで地面と繋がっている。
またがって前後左右に揺らして遊ぶ、公園では定番の遊具。
平日の昼間、部活帰りの私は、小さい頃良く遊んでいたひだまり公園で、クマの形をしたそれに乗っている。大きな頭に寄りかかりながら携帯を片手に、興味はないけれど他にする事もないので何となく「公園 バネ 遊具」と検索しているところだ。
「スプリング遊具って言うらしいわね」
じっとしていても体力が奪われていくような気温だけれど、ちょうど木陰になっていたために鉄で出来たそれ(改めスプリング遊具)は程よくひんやりとしていて心地良い。
実を言うと、このポジションは例の男に会うようになってから見付けた避暑スポットなのである。向こう側に木陰のベンチもあるけれど、ひんやりという部分ではこっちの方が優勢なのだ。暑さから逃れるためならこの際見た目なんて気にしていられない。(女子高生がスカートのままスプリング遊具にまたがり、クマの頭にだらしなく寄りかかっているさまを想像して欲しい)
「ジャングルジムもブランコもシーソーも名前らしい名前なのに、かわいそう」
と、頭に思い浮かんだだけで大して心のこもっていない言葉を口にしながら、クマの尻尾に引っかけていたカバンからパンを取り出す。さっき部活帰りにコンビニで買ってきたハムマヨコーンパン(二十センチくらいある特大サイズ)だ。
「なら君が付けてやると良い」
太陽の光が容赦なく照りつける中、あろう事かジャングルジムのてっぺんに座っている例の男は、暑さなど微塵も感じていないのか、涼しげな顔をしてこちらを見下ろしている。
この例の男について一応説明しておくと、いつだったか偶然この公園を訪れた初対面の私に話しかけてきた、「神様」を自称する電波系の痛い人だ。いまいち良くわからないと思うけれど、私自身も良くわかっていない。
「女子高生がスカートのままスプリング遊具にまたがり、クマの頭にだらしなく寄りかかりながら、二十センチもある特大サイズのハムマヨコーンパンを恥じらいもなく大口開けて頬張っている君に名付けて貰えるならそのクマも本望だろう」
「あなたの中の女子高生像がどんなのかは知らないけど、女子高生っていうのは大体こんなものよ」
「どんなものだろうと興味はないが、そのみっともない姿を君の親兄弟が見たらどう思うだろうね」
「良いじゃない別に見てないんだから」
パンをぺろりと平らげ、一緒に買ったペットボトルのお茶を一気に飲み干す。ぷはーっと声を漏らすと、やれやれ…と呆れんばかりのため息が降ってきた。
「人の目なんて気にしてたらあなたと喋ってないわ」
「ひどい事を言う」
「全力で他人の振りをするわよ」
「ならば僕は全力で知人である事を主張してみせよう。その際には非常にプライベートな部分まであれこれ暴露しなければならないが、」
「やめて」
「認めさせるには仕方のない事だ」
「やめてって言ってる」
「何故神様が人間の言う事を聞かねばならない」
「あなたが神様じゃないからよ」
「そこで君が『私だから』と言えば許してやったところだ」
「訳がわからないわ」
「で、その遊具の名前は?」
「は?」
話の道が外れてすっかり忘れていた。
掘り返すほどの話題でもなかった気もするけど…。
「そうねぇ…」
耳の下から不自然に生えた黄色い取っ手を持って体を後ろにそらしてみると、ギィ…と鈍い音と共にクマも後ろにのけぞる。長い間遊ばれていないようだ。バネが錆付いているのか何なのか、十六歳の女子が力を込めて体重を掛けてもほとんど倒れてくれない。
前へ後ろへ小刻みに揺れながら、そういえば昔こんなダイエット器具が流行っていたような事を思い出した。
「…ロデオ?」
「……君ね」
案の定馬鹿にしたような呆れ顔が返って来る。
「生まれてないだろ」
「そこ!?」
彼の着眼点が理解出来ない。…理解したくもないけど。
一通り呆れ顔を晒したところで、彼はフーン…と唸りながら両手で四角を作り、写真を撮るように片目を瞑りながらこちらを見始めた。
「…何か?」
「そのクマがバイクだったらな」
「バイクだったら何なのよ」
「無免許運転なうって呟けたのにと思ってね」
「……は?」
「いや、流行ってたのさ。昔ね。馬鹿な事をするものだよ。しかしそこが面白いところでもあるんだけど」
「へえ。あなたいくつ?」
「神様にそれを聞くかい?」
彼と普通に会話が成立する日は来るのかと思いつつ、まぁそんな日は来やしないんだろうなと諦めモードな私なのだった。
「落ちてないぞ」
「うるさい!」
もし、この変人が本当に神様だったとするならば、この世界の全ての不条理を彼のせいに出来るのだろうなと思う。こんな男の作った世界ならば、納得出来てしまうような気がした。
今の心の声が聞こえていたのだろう。私をからかう事を楽しんでいた様子だった彼が、急にいつもの、どこか遠くを見据えたような微笑みを見せる。
「僕は神様だ。だが、世界を作ったのは僕じゃない」
神様を自称する奇妙な男は、微笑んだまま、それ以上何も言わなかった。