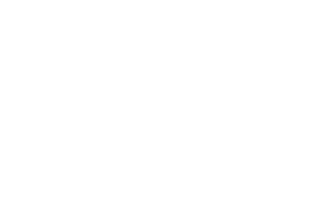No.007 月見る月は此の月の月
中古店で安く買ったと言うママチャリは錆び付いており、漕ぐ度にギィギィと嫌な音を立てる。二人を乗せているともなれば尚更だ。
荒々しくもこちらを気遣っているのか、自転車はゆったりと進んで行く。
「ねえ、月きれい」
自分でもあまり覚えていないのだけど、私は何を思い立ったのか……夜の公園で一人ぽつんと佇んでいた。そこを、コンビニ帰りに偶然通りかかったという彼が拾ってくれたのだ。
こいつとは、私の姉とこいつの両親が同級生だったとかで、かれこれ十四年の付き合いになる。小さい頃から喧嘩ばかりで、今でも顔を合わせる度に憎まれ口を叩いている程だ。
ずっと前を向いていた彼は、ふと上を見上げる。
「どこよ?」
「後ろ。あっちのほう」
「見えねぇよ。あぶねーだろ」
「きれいなのに」
さっきまで空を覆っていた雲が晴れ、姿を見せた月が無数の星と共にきらきらと輝いていた。こうしてじっと空を見上げるのも久しぶりだけれど、こんなにきれいな月を見たのもずいぶん久しぶりな気がする。
ギイィ…という嫌な音を立てて、自転車は走るのを止めた。どうしたのだろうと腰に回していた手を離して彼の顔を見ると、彼は月を見上げていた。そうだな、とも、そうか? とも言わず、じっと空の向こうを見つめている。
こいつは、何を見ているんだろう。
……いや、月のほうを向いているんだから、どう考えたってそれを見ていることには違いないのだけど……なんだか、月を通り越して、何か別のものを見つめているような、そんな気がした。
彼の視線につられて、私も再び空を見上げる。大きな月は変わらずそこにあった。
「ねえ、あのさ」
「なんだよ」
「月から見た私達って、どれくらい小さいのかしら」
「………」
何言ってんだお前、というような呆れた言葉をかけるつもりだったらしい。が、開けた口を静かに閉じて、僅かに息を漏らした。
「地球はたくさんある星の中のひとつで、日本はたくさんある国のひとつで、車巻市は、節木野町は、そこに住んでる私は……きっととんでもなく小さな存在だと思うの」
「………」
彼は黙っている。返事に困っているというわけではなく、話を全部聞いてくれようとしているようだ。
「例えば私がどれだけ辛い思いをして、傷付いて、落ち込んでも、あの月から見た私は想像出来ないくらいちっぽけで……。そんな私の悩みなんて、きっともっとちっぽけなのよ。実はすごく下らないことに、人は一生懸命悩むんだわ。死ぬほど辛いことがあったって、地球はいつも通りに回るし、月は変わらずそこにある。……もし、もしもよ、私が死んだとしても、そうだわ。世界は何一つ変わらないの。そんな、それくらい、世界は大きくて、人間は小さいのよ」
「……何が言いたいのかさっぱりなんだけど」
「そうね……、私も自分で何を言ってるのかわからなくなってきたわ」
「だけどよ、これだけは言えるぜ。地球がどれだけ大きかろうが、月がどれだけ遠かろうが、お前の隣には俺がいるんだ。お前の言う世界ってのが何なのかわかんねぇけど、俺はそいつの見える範囲でしか展開しねぇもんだと思ってる。見えない範囲は別世界ってことだ。俺の世界にはお前がいるし、お前の世界にも俺がいる。あー……。要は、俺達は互いに世界の一部ってわけで、まだガキの俺等の世界は小せぇものだから、一部も欠けちゃならねぇんだよ」
「………」
「もし、お前が死んだら、俺の世界は壊れちまう」
「……そうかもね」
「まぁ、例えばの話だけど」
「そうねー。でなきゃキモチワルくてぶん殴ってるわ」
「あーそーかい! さすが女弁慶は暴力的だな」
「誰が女弁慶よ! タコスケ!」
「タコを馬鹿にすんな! ほら、もう行くぞ」
片足を付き、傾けていた自転車を荒っぽく直すと、私が腰に手を回したのを確認してからゆっくりと漕ぎ始めた。
……中学生のくせに、何一丁前のこと考えてんだか。
私も私だ。特別何に悩んでいるわけでもないはずなのに、どうして急にこんなことを思い立ってしまったんだろう。
有名人でも、大物でもない誰かがどこかで死んでしまっても、この大きな世界は何一つ変わらない。いつも通りに規則正しく動いていく。でも、そばにいた人の世界には、大きな穴が空いてしまう。
「じゃあ、『他人』はどうなのかしら。同じ人というだけで、もしかしたらあの月くらい距離のあるものなのかもしれないわ」
「知らねーよ、他人なんか。俺ぁ両手に抱えきれるぶんさえ守れれば充分だ」
「守る、ねぇ」
「馬鹿にしてやがんな?」
「べーつに。昔から言ってることじゃない。今さらなんとも思わないわよ」
それこそ、耳にタコが出来るくらいに、ずっと昔から聞いていた言葉。
誰をとは言わず、何をとも言わず、ただ「守る」と。
「おめーは月が嫌いなのか?」
「そんなこと言ってないわ」
「嫌ってるみてぇな口振りばっかじゃねーか」
「例えばの話って言ったじゃない。だって……」
ふと前を見ると、遠くの方で明かりの付いた玄関に女性が立っているのが見える。私の姉だ。いつからあそこにいたんだろう。その脇には小さな男の子の姿もあった。そういえば今日合宿から帰って来るんだった。兄はまだ帰宅していないようだが、二人には心配を掛けてしまったらしい。
「だって、なんだよ?」
「だって、好きだもの。月」
月は、暗い道を照らしてくれる。